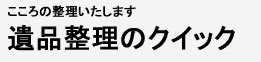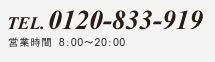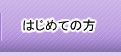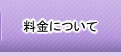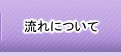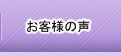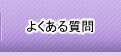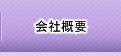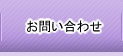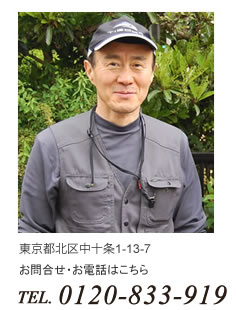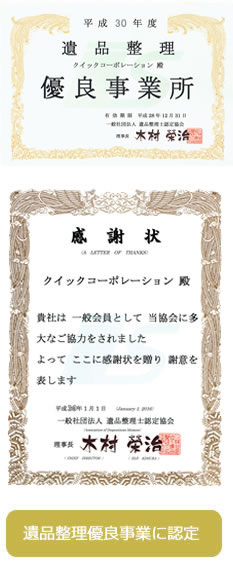2015年7月5日 10:51 AM
【カテゴリ】相続,相続対策
法定相続人とは被相続人が亡くなった時に、相続する権利がある人で、民法で定められています。
配偶者(夫から見れば妻、妻から見れば夫) 常に相続人になります
子供(実子、養子) 認知した愛人の子供、胎児、孫、ひ孫 これらの人を直系卑属といいます
父と母、あるいは祖父母 直系卑属が誰もいないときに相続人になることができます。父と母がいないときは祖父母が相続人と
なり、これらの人を直系尊属といいます。
兄弟姉妹、あるいはその子供 被相続人の直系卑属や直系尊属が誰もいないときに初めて相続人となることができます。
2015年7月3日 6:46 PM
【カテゴリ】相続,遺言書
自筆証書遺言・秘密証書遺言は公正証書遺言と違い、家庭裁判所で検認の手続きを受けなければ、相続登記や預貯金などの名義変更
をすることができません。
遺言書検認手続きには下記書類が必要です
遺言者の住民票の除票
遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍
相続人全員の戸籍謄本
相続人全員の住民票
遺言書原本
上記書類を収集した後に、司法書士等が、検認申立書を作成し、管轄の家庭裁判所に提出します。提出した後に、相続人に対して
検認期日通知書と出欠の確認用紙が送付されます。
検認期日には申立人が出席し、相続人は欠席でも、検認手続きは有効に行われます。
検認終了後に「検認済証明」の申請をして、受け付けられると、遺言書の末尾に「検認を終えたことを証明する」という証明文が
付記されます。この証明文が付されることにより、相続登記などの各種手続きに使用できるようになります。
2015年6月26日 8:16 PM
【カテゴリ】相続,相続の手続き
熟慮期間とは、相続放棄や限定承認が行える期間である。自己のために相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内ですが、例
外的に家庭裁判所の審判によって伸長することができます。
期間の伸長は、3ヶ月の期間だけでは、相続の承認や放棄の判断をするための相続財産の調査ができない場合に認められます。
具体的には、相続財産の種類、複雑性、評価の困難性、所在地に加え、限定承認を行う上での共同相続人全員の協議期間及び財産
目録のの作成期間などの諸事情が考慮されます。
ただし、熟慮期間伸長の申し立ては、熟慮期間の3ヶ月以内に行わなければなりません。